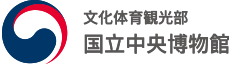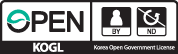758年、美しい比例をもつ双塔が金泉・葛項寺の境内に建てられました。発願者は新羅第38代、元聖王の母である継鳥夫人朴氏と彼女の兄、そして妹です。彼らがどのような懇切な念願を込めて塔を建てたのか分かりませんが、建塔後27余年の時間が流れたのち、継鳥夫人は皇太后になり、その後発願者であった3人は塔に記録されました。

《釈迦塔》に次ぐ美しい比例美
新羅の三国統一は、石塔の姿にも大きな変化を与えました。新羅と百済に代表される各時期の異なる様式の石塔がひとつの姿に再創造されました。7世紀末頃、慶州の感恩寺の高仙寺に建てられた三層石塔がまさにそれです。この塔はまるで統一王朝の権威と威容を象徴するかのように圧倒的な勇壮さと安定的な姿を見せています。最初の層の塔身石上段中央までは底辺が長い三角形構図で安定感を加え、層の間の高さと屋根の比例が一定に逓減し、そのような視覚的効果を見せています。
しかし統一新羅時代初期石塔の安定感と勇壮さは時間が流れるにしたがって早く発展と変化を重ねながら石塔の比例は細長い姿に変化します。塔の規模は縮小し、石を結合して積む方式もまた規則的で効率的に変わりましたが、大きな底辺の三角形構図もまた次第に底辺が狭まる構図に変化しました。8世紀中頃に至ると、下部の正三角形構図と絶妙な逓減率が適用された新羅の歴史上最も美しい石塔が登場します。《釈迦塔》に代表されるこのような比例を持った石塔は、当時首都であった慶州をはじめとして地方でも流行しました。
《葛項寺跡東西三層石塔》(以下、《葛項寺跡石塔》)は、現在失われた部分があるにも関わらず《釈迦塔》に次ぐ、美しい比例を感じることができる理由は、8世紀中頃に流行した比例が適用されているためです。
 釈迦塔、統一新羅、8世紀中頃、仏国寺、国宝第21号
釈迦塔、統一新羅、8世紀中頃、仏国寺、国宝第21号
 《釈迦塔》作図(図面作成:米田美代治)
《釈迦塔》作図(図面作成:米田美代治)
塔表面の多数の釘穴]
《葛項寺跡石塔》には独特な特徴があります。《釈迦塔》やそれ以前の時期に制作された標準型の石塔からは、ほとんど探し求められない表現で、塔表面全体に多数の釘穴があるという点です。

標準型の石塔が出現した7世紀末から、比例が完成する8世紀中頃に至るまで、石塔の表面に釘穴を開ける場合は、屋蓋石に風鐸を掛ける場合を除いては、ほとんど見られない表現です。もちろん、これより早い時期に制作された《高仙寺跡三層石塔》の初層塔身石にもこのような穴の表現が見られますが、長く流行はしなかったようです。《高仙寺跡三層石塔》の穴の用途は金属板のような装飾物を付着するためのものと推定されます。
このような装飾的な表現をした塔が、どのように慶尚北道金泉の深い谷間にあったのでしょうか。塔の基壇部部材の配列方式および各部材間の比例などは、758年に建立されたという銘文の記録を信頼させてくれます。
慶州でこれと似た石塔の例は《伝仁容寺跡東西三層石塔》を挙げることができます。8世紀後半に制作されたと推定されるこの双塔は、長い時間倒壊したまま多くの部材が遺失しましたが、屋蓋石と初層の塔身石においてこの塔と類似性を探し求めることができます。とくに屋蓋石の釘穴の配列は、《葛項寺跡石塔》のそれと違いがありますが、端に沿って一定の間隔で開けられた点は、似た荘厳意匠を見せています。このようにこの双塔は表面荘厳の発展段階側面から見る時は、《高仙寺跡三層石塔》と《葛項寺跡石塔》の間の空白を埋めてくれる中間段階の遺物と見られます。

2 《伝仁容寺跡三層石塔》 屋蓋石と初層塔身石
3 《葛項寺跡東西三層石塔》 南側面屋蓋石と初層塔身石
しかしこれは先に考察した《葛項寺跡石塔》と《伝仁容寺跡石塔》の制作時期と相反します。
このような問題は、《葛項寺跡石塔》の銘文に刻まれた時点とその背景に自然と関心を傾けさせます。

“両塔は天宝17年(758)年、兄と姉妹、3人の業で完成した。兄は慶州霊廟寺の言寂法師で、姉は昭文皇太后で、妹は敬信太王の母方の叔母です。(二塔天寶十七年戊戌中立在之 娚女市妹三人業以成在之 娚者零妙寺言寂法師在 女市者照文皇太后君妳在 妹者敬信太王妳在也)”
敬信太王と昭文皇太后は、『三国史記』の記録にも確認できる人物で、それぞれ元聖王と彼の母を指称しています。王という表現と諡号でない敬信という諱が使用された点などから見て、銘文は元聖王の治世期である785年から798年の間に刻まれたことが分かります。ところでなぜ塔の建立当時でなく元聖王の在位期間中に王との関係に言及し、発願者はこの塔に銘文を刻んだのでしょうか。ひょっとすると、敬信が王になった後、彼の外戚が彼らの願刹であった葛項寺にこれを記念するため仏事を行ったのではないでしょうか。当時行われた仏事の規模は分かりませんが、塔に残っている釘穴と銘文はそのような隠された事情を注意深く聞かせてくれているようです。
このように《葛項寺跡石塔》の独特な特徴である釘穴は、建立当時でなく元聖王の在位期間中に表面の荘厳のために新たに開けられたもので、その技法は新羅王城のすぐ近くに建てられた《伝仁容寺跡石塔》などをモデルにしたものと解釈してみると、今まで様式史的に理解されてこなかった疑問点が自然に解決します。
初層塔身石中央の粗い面処理の痕跡

《葛項寺跡石塔》のもうひとつの特徴のひとつは、初層塔身石の中央部が粗く処理されている点です。普通このような粗い痕跡は直接露出しない部位などで見られる特徴で、初層塔身石中央部ではたいへん異例な処理と言えます。
早い時期に高裕燮(韓国の初代美術史学者)先生が元々ここに四天王像や菩薩像のようなレリーフが刻まれた可能性を提起して以来、異なる見解が提示されたことはなく、粗い痕跡が明確によく残っています。この痕跡は先に考察した釘穴と共にこの塔の理解において、注目しなければならないもうひとつの部分と言えます。
その理由は《葛項寺跡石塔》建立当時には、初層塔身石にレリーフが刻まれていましたが、以降元聖王在位期間中に石塔を追加荘厳する過程で既存のレリーフ像を無くし、その位置に金属板を付けた可能性を知らせるためです。このように初層塔身石の中央部の粗い面の処理痕跡は、石塔表面に釘穴が開けられた時期が元聖王の治世期であるという推定を改めて確認させてくれています。
依然として多くの疑問をもつ《葛項寺跡石塔》
《葛項寺跡石塔》は、美しい比例美と758年という絶対年代が残っており、統一新羅時代石塔研究においてたいへん重要な資料です。先に考察した内容以外にもこの両塔には依然と多くの疑問点を残しています。ほとんど同一の双塔のなかから発見された舎利荘厳具もまた細部の形が少しずつ異なり、そのなかから出た《准提真言》、そして舎利荘厳具の出土位置など今後もこの塔の研究のため解決しなければならない多くのパズルが残っています。